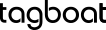海岸和輝・個展アーティストインタビュー「色の相互作用から生まれる幾何形態」
東京藝術大学油画専攻を卒業し、グラフィックデザイナーとしての活動を経て、2020年より本格的に絵画制作へ回帰したアーティスト・海岸和輝。デジタルドローイングの経験を基盤に、「線を引く/消す」という根源的な行為を画面上で往復させながら、色彩の知覚や視覚的な“相互作用”を探究してきました。
一見デジタルのようでありながら、キャンバス上に丹念に再構築された筆致は、幾何学的な構造と揺らぎのバランスを保ち、色同士の“作用と反応”が生み出す独特の世界を生んでいます。
今回のインタビューでは、個展「Interaction」に込めた思いや、デジタルとアナログの往還から生まれる表現の本質についてお話を伺いました。
海岸和輝 Kazuki Umigishi
1984年東京都生まれ
東京を拠点に活動
東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業
卒業後はいったん絵画制作から離れ、グラフィックデザイナーやミューラルアーティストとして活動したのち、2020年より本格的に絵画制作を再開。現在は主にアクリル絵具を用い、キャンバスや変形パネルに制作を行っている。グラフィックデザインの経験を背景にデジタルドローイングへ取り組む中で、線を描くことと消すことが絵画における根源的な行為であると考え、デジタルの筆致を基盤とした抽象表現を探求してきた。その過程で、色彩の知覚や相互作用への関心を深めている。絵画の歴史において、画家たちは画面上で「嘘」を重ねることで独自の世界を構築してきた。色彩にもまた、現実とは異なる感覚や認識を引き起こす「嘘」が潜んでいる、その視覚的作用や知覚のずれに注目し、色を中心とした表現の可能性を探究している。
色の相互作用から生まれる幾何形態
tagboatでは2回目の個展となりますが、今回はどのようなテーマやコンセプトで展示を構成されましたか?
前回の個展は2023年の年末で、私にとって初めての個展でした。貴重な機会をいただいた喜びと、空間をきちんと成立させられるかという不安の狭間で、手探りのままなんとかやり切ったという感覚が強く残っています。あれからちょうど2年が経ち、今回はその間に積み重ねてきた成長をしっかりお見せできればと思い制作に取り組みました。
今回の展示テーマは「Interaction(相互作用)」です。
私は、線を引くことと消すことが絵画の根源的な要素だと考え、これまでペンツールによるブラシストロークと消しゴムツールを使用してデジタルとアナログを行き来しながら制作してきました。
その過程で、画面の中で生じる色の知覚や相互作用に強い関心を持つようになり、近年はその部分をより深く研究しています。色は絵画において相対的な存在で、サイズや配置、隣り合う色の影響によって大きく表情を変え、さまざまな知覚を生み出します。
今回の展示では、そうした色同士の影響の連鎖を、作品を通じて感じ取っていただければと思っています。

今回、新しく試みた技法や表現手法があれば教えてください。
同じような絵を描き続けていたら自分が飽きてしまうのですが、一枚仕上げるたびに新しい発想やアイデアが浮かんでくるので、それらを少しずつ試しながら制作を続けています。そのおかげで、毎日楽しく描けています。
今回の展示には、シェイプドパネルで過去作と同じ形を用いながら、配色だけ異なる作品があります。これはカラーバリエーションを作るためではなく、ゼロから描くと似た配色に寄ってしまうことがあるため、あえて形を固定し、その上で新しい配色の可能性を探るための方法として行っているものです。
また、展示中の作品をスマートフォンで斜めから撮影した際に生じる歪みを、そのまま絵画として再構成するような試みも行っています。
小さな実験を重ねることで、自分でも予期しない表現が生まれるのを楽しんでいます。

制作中に「嘘を織り交ぜる」とありますが、その“嘘”とはどのようなものですか?
「嘘」というと語弊があるかもしれませんが、絵画における演出のようなものを指しています。遠近法や光の加減、さまざまな具象化の方法など、実際とは異なる処理をすることでリアリティが生まれたり、作家性につながったりする、そういった要素のことです。
私の作品でいえば、色が重なって見える部分の混色のルールがあります。本来であれば加法混色や減法混色が成立するはずなのに、あえてそうならない色を置いたり、全く別の色として見えるようにしたりしています。
そうした“嘘”を織り交ぜながらも、画面全体としては破綻させずに成立させる、そういう試みを行なっています。

画面を構成するとき、まず“色”から入るのか、“構図”や“感覚”から入るのか、プロセスを教えてください。
まずは構図から入ります。
下絵はPhotoshopとペンタブで作成しているのですが、色は仮置きで形としての画面構成を完成させてから色を決めています。デジタルのいいところは何度でもやり直しができるので、納得のいくまで画面上でやり取りをして作っていきます。
最高のイメージが出来たと思っても一晩以上寝かして、もう一度冷静になってから確認してまた修正を繰り返してクオリティを上げていきます。

制作の中で「偶然性」はどの程度関わっていますか? 意図と偶然のバランスについて教えてください。
学生の頃は、ポロックのように絵具を撒いたり飛び散らせたりする、偶然性に頼った抽象画を描いていました。しかし、ある時期から画面上で絵具が混ざることに苦手意識を持つようになり、今のスタイルにたどり着くまで、10年以上絵が描けませんでした。
デジタルで下絵を作ると偶然性がなさそうに思えるかもしれませんが、実際には自分でも完全に把握できていない効果や処理を多用しているため、思ってもいないイメージが生まれることがあります。ただ、その下絵をアナログ作業で描く段階では、ほとんどイメージどおりに再現できるので、制作中に大きな偶然が入り込むことはあまりありません。
偶然性をどう作品に取り込むか、そのバランスをどう調整していくかが、今後の課題だと考えています。

これまでの人生や創作活動の中で、特に影響を受けた人物や作品はありますか?その理由も教えてください。
高校時代の美術の先生や美術予備校の先生が言っていたことは今でもよく思い出します。
あの頃は何を言っているのかよくわからなかったことも、最近になってようやく体感できたり納得できたりということが多いです。
10代の頃に、ただがむしゃらに描く中で心に植えられた「種子」が、長い時間をかけて、ようやく芽吹き始めたという感覚です。時間がかかっていますが、焦らず、ゆっくりと育てていきたいと思っています。
鑑賞者の反応やコメントが制作に影響することはありますか?
直接的に鑑賞していただいた方の反応で作品が変化することはありませんが、観ていただいた方とお話する中で予想外の反応やコメントをいただくと、とても面白く励みになります。
たまに買う気がないのに見に行っていいのかしらとか、手ぶらで行ったら申し訳ないと仰ってくださる方がいらっしゃいますが、見てもらえるだけで嬉しいので、お気軽に手ぶらでお越しください。

今後の制作において挑戦したいことや意識したいことはありますか?
先ほども少し触れましたが、偶然性をどうやって落とし込んでいくかを考えています。そもそも自分の作品に偶然性が必要なのかというところから考えなくてはいけないのですが、現状ではデジタルからアナログへの変換においてキャンバス上で色の調整はしていますが、ほぼイメージをそのまま落とし込めているのでそこに手作業の揺らぎをどの程度入れ込むかは検討中です。
あとは単純に今まで描いた事ないぐらい大きい作品をもっと描いていきたいです。
12月12日(金)からギャラリーにて個展「Interaction」を開催いたします!
海岸和輝「Interaction」
2025年12月12日(金) ~ 12月25日(木)
営業時間:11:00-19:00
休廊:日月祝
※初日の12月12日(金)は17:00オープンとなります。
※オープニングレセプション:12月12日(金)18:00-20:00
※12月18日(木)は、諸事情により18:00閉場とさせていただきます。
入場無料・予約不要
会場:tagboat 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-1 ザ・パークレックス人形町 1F
関連する記事
Category
Pick Up
- 友成哲郎・アーティストインタビュー「人をめぐる欲求のかたち」
- 新埜康平・アトリエインタビュー「二つの文化が交差する新たな日本画の地平」
- 池伊田リュウ・アーティストインタビュー「視界を追い、生命と自然を考える」
- HARUNA SHIKATA・アーティストインタビュー「過去を上書きし、現在を描く」
- 都築まゆ美・アーティストインタビュー「二面性のあいだに揺れる、普遍の物語」
- 月乃カエル・アーティストインタビュー「それでも世界は美しい」
- 石川美奈子・個展アーティストインタビュー「線と色が現象を可視化する。」
- 海岸和輝・個展アーティストインタビュー「色の相互作用から生まれる幾何形態」
- 市川慧・個展アーティストインタビュー「目に見えないものを想像することの大切さ」
- 有村佳奈・個展アーティストインタビュー「本物とは何か、AI時代のリアルを描く。」